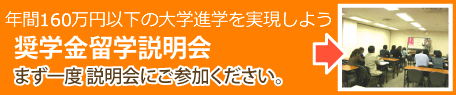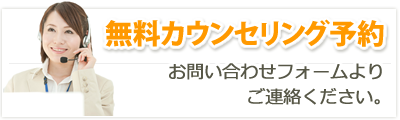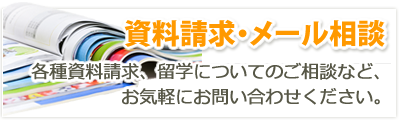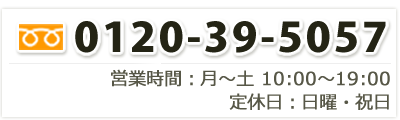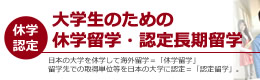海外留学のグローバルスタディトップ > アメリカ大学留学奨学金プログラム > 体験談一覧 > ウィスコンシン大学スタウト校
アメリカ大学留学奨学金体験談(ウィスコンシン州)
ウィスコンシン大学スタウト校(University of Wisconsin-Stout)
慣れない環境に自分を適応させることは意外と楽しい作業

- 太田代 和人 さん
- ウィスコンシン大学スタウト校(University of Wisconsin-Stout / ウィスコンシン州)
- 大学での専攻:Studio Art: Art Photography concentration
- 日本での出身校:都立国際高等学校
- 留学期間: 2023年9月~(卒業予定)2027年5月
留学前について
留学前はどんな学生生活を送っていましたか?
部活に委員会、放課後にはプログラミング教室に通うなど忙しい高校生活だったと思います。しかし、周りの友達と少し違ったのは、僕の場合高校に入学した時点で海外の大学に進学したいとなんとなく考えていたため選択制の授業は英語に集中し、受験勉強もそれほど苦労はしませんでした。
なぜ日本の大学ではなくアメリカの大学を選んだのですか?
元々人生の大半を海外で過ごしていたので、日本に留まって勉強することに違和感を感じていました。自分と自分の言語能力を試し、日本の縮こまったコミュニティーから抜け出したいという思いが強かったです。アメリカを選んだ理由は様々ですが、人種多様性や選べる大学の多さなどが思い浮かべやすいです。あとは単純に世界のあらゆるスタンダードの一つを体験したいと考えたからです。
なぜ奨学金留学プログラムを利用したのですか?
アメリカの学校を探し、奨学金も一人で探して応募するとなると、相当苦戦すると思います。僕も実際、私立か州立、美大か普通の大学、費用や奨学金で数ヶ月悩んでいたところこのプログラムを見つけて助かりました。アメリカの大学に通うとなるとほとんどの学生が奨学金や何かしらの経済的援助が必要になると思います。このプログラムは大学選びと奨学金探しがセットで出来るのでとても便利でした。
なぜ、今の大学を選びましたか?
僕はこの大学の講義より実習や実際手を動かす授業を重宝するポリテクニックな一面に魅力を感じました。さらに、美術系の道に進みたかったため、美術系専攻が幅広くオファーされている大学を選びました。また、中西部のど田舎にあるということで、都市部の日本人コミュニティーをあえて避ける形でこの大学を選びました。自分が慣れているものから完全に隔離された環境で勉強に没頭し、普段会わない人と交流出来たらいいなと考えたからです。
留学前に感じていた不安はどのようなことでしたか?
大きな不安は特にありませんでした。強いて言うなら、新生活を自分の思い描いたように送れるのかだとか、ご飯はどれだけ不味いのかなどが挙げられますが、どれも慣れてみればどうって事ないものでした。
どのように英語学習を進めましたか?また、TOEFLやIELTSのスコアアップに取り組んでいる方にアドバイスがあれば教えてください。
僕の場合は英語、特に読み聞きが得意だったので、とにかく話す書くを磨き上げました。これに関しては、高校の外国人教師を最大限に頼りました。パーソナルエッセイやTOEFLのプロンプトをコツコツと書いては添削してもらうを繰り返しました。添削して、より効力のあるエッセイを作り上げるプロセスでその外国人教師と会話・交流出来たら一石二鳥です。また、エッセイを書く中でいろんな単語の言い換えが必要になってくると思いますが、シソーラスを活用してさらにボキャブラリーを広げました。書く技術は入学しても必ず必要になるので一番力を入れた気がします。
留学中について
留学先で一番大変だったことは何ですか?
地味ですが、正しい食生活を保つことです。毎日授業と課題で忙しいので基本カフェテリアで食事は済ませていますが、日本の食堂に比べてカフェテリアは品数も少なく、ジャンクなものばかり提供しているのです。その中で、脂質と炭水化物だけでなくしっかりタンパク質や食物繊維を摂ることは、かなり重要だと思います。また、昼と夜だけでなく、朝ごはんもなんでも良いので食べることが重要だと気づきました。朝8時から始まる授業は、まだ眠いし、あまり集中できません。ですが、朝食をとることで目覚めますし、集中力が長続きします。良い食生活を保つことは留学先で健康でいる事、虫歯を予防する事、正しい生活リズムを確立し効率的に勉強する事に直結すると振り返ってみて思いました。自炊もなかなか大変ですが、日本の料理を食べると心の安らぎにもなるはずです。大袈裟かもしれませんが、重要な事です。
留学先で挑戦したこと・がんばったことを教えてください。
僕はいつも過ごしていた仲間がみんなインターナショナル生だったので、もっとアメリカ人と積極的に交流する事を頑張りました。そもそも、奨学金を得るために1学期20時間以上のボランティアをしなければいけなかったので、自然とその横のつながりは広がっていきました。ですが、授業などで友達を作ることがかなり難しかったです。あまりにも共通のものが少なかったのかノリが違ったのか。ですが、本当にオシャレだなと感じた人に声を掛けてフォトシュートをお願いして仲良くなったり、一緒に何かアートを作りましょうなどとコラボレーションを持ちかけたりしてきっかけを作っていきました。
留学をする前と現在では、自分の何が変わりましたか?
積極性が増しました。やはり自分から行動しないと何も得られない社会なので、自分の成長の為に必要なものは遠慮なく獲得していきました。また、それが自然とできるようになった気がします。人に話しかけるのも、わからない事を聞くことももっとできるようになりました。一回日本に帰ってみて思った事が、何かを遠慮したり規則をきっちり守ったりすることが馬鹿馬鹿しくなりました。どんどん英語脳・アメリカ脳になってる証拠なのだと思いますが、日本のやり方、西洋のやり方、どっちとも理解するのが大事なのだと気づきました。
今振り返ってみて、留学前にしておけばよかったと思うことはありますか?
もっと日本の事をもっと知っておけば良かったと思いました。歴史や政治など、急に授業で日本はどうなの?と聞かれる事も有れば、友達から質問される事も多々ありました。国際交流の第一歩は自国について知ることなのだと改めて思い知らされました。また、日本のお菓子や手拭いなどちょっとしたお土産を持って行って仲良くなった人にプレゼントするのも良いなと思います。めちゃくちゃ喜ばれますし、仲が一層深まります。
留学で得たことは、今後の人生・キャリアにどのように生かせると思いますか?
間違いなく活かせると思います。留学で得た知識や経験は大抵の日本人が得たものよりも特異で貴重なものだと感じます。なんというか、箱の外から考えられるようになると思うのです。日本で今後自分のキャリアを築こうかどうかにかかわらず、自分がいるだけで、自分がいるコミュニティーに別視点の、ユニークな意見を取り入れる事ができると思います。日本のやり方に捉われない、自分なりのやり方を何事においても適用する事ができることはアドバンテージだと思います。人生においては、留学がきっかけで横のつながりが増える事もあると思います。
留学をしてよかったと思いますか?
思います。
大学生活について
大学のサポート体制はどうでしたか?

とても充実していました。特に重宝したのは以下の3つです。
一つ目はアカデミックアドバイザーです。自分の専攻に必要な必修授業、選択授業、単位数などについてアドバイスをくれる人がいるので、間違って別の授業をとってしまって困ることがありません。仮に、履修登録の競争(日本の大学では抽選形式もあるようです)に失敗して、取りたい授業や取らなきゃいけない授業が取れなくても、アドバイザーが代替案を提示してくれます。
二つ目は、OIE(Office of International Education)職員です。インターナショナル生は困り事があれば最初にここを尋ねます。ビザ、保険、奨学金など柔軟に問題に答えてくれますし、普段の生活の悩みなども聞いてくれます。
最後にライティングセンターです。エッセイの添削やライティングの悩みは全部ここで解決できます。エッセイ課題のテーマが思い浮かばない、参考文献が見つからない、フォーマットがよく分からない時に助けてもらいます。課題だけでなく、奨学金用のパーソナルエッセイやアメリカ式の履歴書の書き方も教えてもらえるので便利です。
寮生活で良かったことは何ですか?
僕が入った寮はインターナショナル生が多く住んでいる寮でした。アメリカ人の他にスペイン人、ドイツ人、中国人、インド人、韓国人、ベトマム人など多種多様でした。その中でいろんな人と関係性を築くのがとても楽しかったです。
ルームメイトはアメリカ人でした。清潔感があり、コモンセンスもしっかりしている人だったので、共同生活は全く問題なかったです。友達にもなれましたし、中西部の人はこんな感じなのだなと興味深い人間観察もできました。
寮生活で困ったことはありましたか?
困ったことは色々あります。やはり日本人だからでしょうか、トイレやキッチンの清潔感はとても気になっていました。トイレは毎度汚れているし、キッチンはゴミがそこら中に落ちていて、自分で掃除をしていると清掃員のおばちゃんに感謝感激されるほどです。
他にはルームメイトと生活リズムを多少合わせなければいけない事です。アメリカ人はどうやら17時半には晩ご飯を食べ、23時前には寝てしまうのです。元々夜型だった僕は、ルームメイトを起こさないために、色々工夫はしましたが、結局自分も23時に寝ることで生活リズムを改めました。ですが、逆に27時までコンピューターを全稼働しゲームをする人もいたので、当たり外れはあります。
最後は食に困りました。毎日カフェテリアで昼と夜ご飯を済ますのですが、毎回選べるメニューがハンバーガー、タコライス、パスタ、ピザなどしかなく飽きます。また、積極的に食事のバランスを考えて食物繊維などを摂っていかないと体調を崩しやすくなります。もちろん日本食が恋しくなるので、週に2、3回は自炊をしていたのですが、課題で忙しい時は全くできない時もあります。日本で手に入る食材や調味料も少ないので、隣町に買い出しに行くなど工夫をしていました。
休日は何をして過ごしていますか?
小さい町の中に大学があったので、それほどレクリエーションはありませんでした。基本的には課題を済ませ、寮の中でビリヤードや卓球を友達としていました。時には映画を見たり、バーに忍び込んだり、隣の小さい町までドライブするなどしました。小さい連休があれば、友達と隣町のミネアポリスへの小旅行を計画し、エアビに泊まって楽しんでいました。学期の後半になってくると、課題やプロジェクトで忙しくなり、美術系専攻の僕はアトリエで一日中デッサンをしていました。
大学で、勉強以外に取り組んでいることがあれば教えてください。
一つはボランティアです。奨学金をもらうためには、良い成績と20時間以上のボランティアが必要なので、暇な時はボランティアをしていました。色んな学生団体が催しているボランティアイベントに参加したり、学生団体に入って企画をしてみたりしていました。
他には写真が趣味だったので、学生経営のビジネスの商材写真だったり他の美術系の学生とフォトシュートをしたりしていました。
どのようにして友人ができましたか?
僕は大学初日のインターナショナル生向けのオリエンテーションで、周りに座っている人から声をかけて友達になりました。ただでさえ、小さいコミュニティですのでアメリカ人以外と仲良くなるのは簡単でした。授業でも、クリティークやグループワークは必ずやるので、自然と知り合いは増えます。中西部のアメリカ人は内向的な人が多く、もう既に存在している友達のグループに固執しがち(シャイ)なので、共通の趣味などを通してその壁を攻略して行かなければならないと気づきました。僕の場合はファッションや趣味のバスケットボールなどで人と繋がることが多かったです。
周囲の学生にはどんな人がいましたか?
前の質問でも書きましたが、中西部のアメリカ人はシャイな人が多いです。その点ではなかなか日本人と共通しているのではと思うのですが、本質はとても好奇心旺盛です。仲良くなってみるとめちゃくちゃ話しかけてくれます。ほとんどの人がウィスコンシン州もしくはアメリカを出たことがなく、飛行機すら乗ったことがない人もたくさんいます。中にはアニメや漫画、日本のゲームなどにとても関心がある人もいるので、気が合う人もいるかもしれません。他にはモング人(中国系の一族)、インド人、中国人が多くいました。彼らはそれぞれ既に大きいコミュニティが確立されていて、モング人以外は他のアメリカ人やインターナショナル生と仲良くしている印象はありませんでした。特に中国人留学生は英語すらほとんど通じませんでした。
アメリカという国や、滞在されている州や都市について感じたことを教えてください。
僕がいたウィスコンシン州はアメリカの中西部、五大湖の隣に位置する北側の州です。一番大きい都市はミルヲウキーですが、僕がいた町からは隣のミネソタ州のミネアポリスの方が近かったです。ウィスコンシン州はほとんどがトウモロコシ畑で覆われていて、田舎そのものです。人々は皆温厚な性格で、外から来た人にもウェルカムな感じでした。その反面、アメリカからもしくはウィスコンシンから出た事がない人たちが多く、外の世界を知ろうと外国人には興味津々です。気候は常に極端で、一年の半分以上は真冬、気温は-25℃まで余裕で行きます。
夏休みなどの長期休暇期間は何をしましたか?
夏休みは4ヶ月間日本に帰り、バイトやインターンをする予定です。冬休みは友達と旅行の計画をたて、ロスアンゼルスに一週間滞在したり友達の実家に泊めてもらったりしていました。
大学での勉強について
留学先の大学では何を専攻していますか?それは何故ですか?

Studio Art - Art Photographyを専攻しています。
僕が通っている大学は少し特殊で、普通美術系の学科を専攻したい場合はポートフォリオが入学時に必要ですが、UW-Stoutの場合Pre BFAというプログラムが代わりにあります。これは、最初の一年にデッサンやデザインなど美術の基礎授業を受けるものです。そして、一年の最後に今までに取り組んできたプロジェクトをまとめたポートフォリオを提出して希望専攻の合否を決めます。元々は応募されるポートフォリオのクオリティに納得がいかなかったので、学生の技術とセンスを鍛え選別する目的で導入されたシステムだそうです。
僕の場合、元々Graphic Designを希望していましたが、いろんな教授からスタジオアーティストを勧められ専攻を変えました。元々写真に興味がありましたし、最初の一年で取った写真の授業が楽しかったので、Art Photographyに変えました。ある意味、UW-StoutのPre BFAプログラムは、数ある美術専攻をじっくり考えて選択させてくれる良いシステムだと思っています。
今までの授業で一番大変だった内容・科目は何ですか?
強いて言えば英語のComposition 1・2でした。Argument、Summary & Response、Exploration/Synthesisエッセイなど、様々なエッセイの種類を学んで書く授業です。特に、優れたレトリックを意識して書かなければいけないので、どのエッセイも完璧に点数を取ることが難しかったです。
さらに僕は春・秋学期ともに5つの授業中3つのラボ授業(実技中心のもの):デッサンやデザインの基礎、写真学等を取っていて、3つのプロジェクトが同時進行になることが多かったです。これは課題の締切前に特に忙しくなることが多く、徹夜やスタジオに何時間も篭るシチュエーションが多かったです。しかし、その代わり周りより作品の質において差をつけられることができました(ほとんどのアメリカ人は課題を真剣にやらないので)。
お気に入りの授業があれば理由も含めて教えてください。
写真術の、Alternative Process Photographyという授業が楽しかったです。普段のアナログ・デジタル写真とは別のアプローチで写真を学びます。アンソタイプや青写真など一週間に一プロセス学んで作品を作ります。この授業はアドバンスドな授業でしたが、知らずに取ってしまいました。クラスメイトは3、4年生ばかりで自分はただ一人のフレッシュマンでしたが、逆に張り合いがあって良い経験になりました。
どんな教授がいましたか?
ここではほとんどの教授が楽天的です。課題の採点や試験のルール(オープンノート)などとてもゆるい気がします。基本皆アプローチしやすく、対等な関係で接してくれます。真面目に授業に取り組んでいれば、何かミスしてしまった時(遅刻、課題の出し忘れ等)にボーナス課題で挽回させてくれるチャンスをくれます。美術系の教授もやはり楽天的で、日本の美大や画塾などでありがちな劣っている点を評論するのではなく、優れている点をどんどん褒めてくれます。教授らは彼ら自身アーティストであることが多いので、生徒からの信頼とリスペクトはすごいと思います。
一日どのくらいの勉強時間を取っていますか?主にどこで勉強していますか?
授業時間は1日に4~6時間くらいあります。大半が実技授業で、講義は1時間のものが多いです。自習は1日に3時間以上は費やします。基本的にその日に出された課題を終わらせて、エッセイであればできるところまでやっていました。場所は主に図書館か寮の自習スペースでした。また、友達と勉強会をやっても気が散って一人の時よりも作業効率が格段に減るため、そこははっきり線をひいていました。そのほかに、デッサンや作品作りに充てる時間が一日に3,4時間ほどあります。これは人によって様々だと思いますが僕はもっと上手くなりたいし、他と差をつけたかったので、結構夜遅くまで追い込んでいました。
アメリカの大学で学んでみて、日本の教育と違う点は何だと思いますか?
まず、課題が多いです。ほぼ1日に一個こなさなければいけないくらいのペースで課題を詰めてきます。僕の考えだと、一つのプロジェクトや議題に対してのプロセス一個一個を丁寧に教えるためにしていると思います。また、課題の点数のウェイトが重いので、日本のように期末試験で一発勝負なんて事はあまりありません。もう一つ、講義のスタイルが自由です。日本の講義は教授が前で喋っていて、生徒はメモを取る形式が多いと思います。ですが、ここでは生徒間教授間のアクティビティ要素がかなり多いです。グループワークや教授から投げられた質問に答えるなどどの授業にもあると思います。そして、講義中だとしても、教授に質問や意見が出た時に、それに乗っかって小さいディスカッションになることも多々あります。それが自由にできる環境、教育思想なのだと思いました。
アメリカの大学授業についていけるかどうか心配される日本の学生は多いです。アドバイスがあれば教えてください。
僕は、その緊張感があれば逆に大丈夫だと思います。ついていけるか不安で、ついていく努力をしていれば教授や周りの人は必ずサポートしてくれるはずです。アメリカ人は不真面目な人が圧倒的に多いと思うのです。やることをしっかりやっていれば結果はちゃんとついてきます。それでも不安だったら積極的に教授やライティングセンターやクラスメイトのサポートを活用するのです。でも、それは自分から行かないと誰も助けてはくれません。
最後に
アメリカの大学に進学するかどうか悩んでいる方に向けて、アドバイスをお願いします。

僕は留学する数年前から日本から出たいという願望が強かったので、留学するという選択はそれほど重いものではありませんでした。しかし、それを悩む方がいるのであれば思い切ってしてみれば良いと思うのです。もちろん費用はかかりますし、自分で学校や奨学金をリサーチするのも難しいです。そのための留学プログラムなのですから、それを上手く活用しましょう。また、僕は未知の環境に自分を置くことに何もデメリットはないと思うのです。実際僕も人口1万5千人しかいない田舎の町の小さな大学に馴染んで楽しめるか最初は不安ばっかりでした。ですが、全て新しい経験として吸収できたし、慣れない環境に自分を適応させることは意外と楽しい作業、住めば都です。勉強面もサポートは充実していますし、日本の大学で日本人に囲まれて勉強するより得られる経験は多いと考えます。大学を終えるとアメリカに留学する機会もそうないと思うので、もう一度考えてみてはいかがでしょうか。